「津久井湖畔に植生浄化施設」を施工
棚田式の浄化施設は多様な動植物のビオトープとして環境学習にも最適です
2002年12月03日
- ◆キーワードは、「植生浄化」、「ビオトープ」、「市民参加」、「環境学習」
- ◆ダム湖畔における棚田式の植生浄化は、全国でも初めての試み
■このニュースのポイント■
神奈川県北部の津久井湖畔に水質浄化施設であり、動植物の生息空間でもある新しいタイプの「棚田」が誕生しました。この棚田には、周辺住民が参加する「つくいビオトープ推進委員会」の活動が反映されています。
東亜建設工業は、これまで生活雑排水や湖沼・河川水、海水等の抱えるさまざまな環境問題に取り組み、水質浄化の一対策として植生浄化「東亜リビング・フィルター」を提案してきました。そしてこのたび、「植生浄化」機能に加えて、「ビオトープ」、「市民参加」、「環境学習」をもキーワードとする「棚田式の植生浄化施設」を施工しました。

津久井湖畔の「棚田式の植生浄化施設」
●背景
湧水の枯渇や河川流量の不安定化など水をめぐるさまざまな問題から、環境保全に果たす水の役割を見直そうという動きが高まっています。自然の水循環の恩恵を享受しながら、人間社会の営みとどのようにバランスを取るべきなのか、一人一人が考えるべき時期にきています。
こういった背景のもと、豊かな水辺づくりにつながるよう、このたび当社は親水性の高い「棚田式の植生浄化施設」を施工しました。
●「棚田式の植生浄化施設」の概要
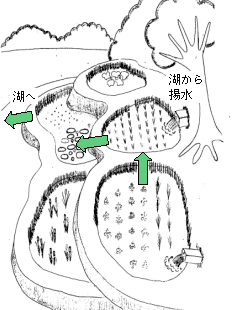 棚田イメージ図
棚田イメージ図
東亜建設工業は2001(平成13)年度、津久井湖畔に神奈川県企業庁利水局発注の植生浄化施設を施工しました。津久井町三井地区に一部完成した同施設は、法面を活かした棚田の形状をしており、今年度さらに棚田の増設に取り組んでいます。
同施設は湖水をポンプで揚水し、棚田の植物帯を循環させて水質浄化を図ったのちに湖に戻すもので、「つくいビオトープ推進委員会」の考えを取り入れてハス、ハナショウブ、アサザ、クレソン、セリなどを植えました。棚田はやわらかなカーブを描いた石積みの護岸に支えられる構造で、周辺環境との調和が図られており、棚田を循環する水のせせらぎは心和ませてくれます。また、棚田の間にはゆったりとした歩道がめぐらされており、動植物とふれあう環境学習の場としても最適です。
今春には棚田に湖水が循環し、植裁した植物は順調に育って花を咲かせました。棚田によるSS(浮遊物質)やCOD(化学的酸素要求量)、栄養塩等の除去効果については現在検証中です。生物調査では昆虫のほか、両生類や魚類なども確認されています。今後、貴重なビオトープに発展できる可能性が膨らんできました。施工業者として、今後もさらに棚田の有効性を確認していきたいと考えています。
●「棚田式の植生浄化施設」の主な特長
「棚田式の植生浄化施設」の主な特長は、次のとおりです。
- (1)植生浄化施設では、水中の汚濁物質が植物体と接触して沈降し、
また、リン・窒素の吸収・脱窒・吸着作用によって除去されます。 - (2)さまざまな植物帯は水生昆虫や両生類、魚類などの隠れ場所や餌場、
産卵場となり、多様な生息空間を創出します。 - (3)動植物とのふれあえる棚田は、環境学習の場として活用でき、また、憩いの場になります。
- (4)「つくいビオトープ推進委員会」を通じて、周辺住民の意見が反映されています。
- (5)既存の地形(法面)や樹木を有効活用しています。
●今後の展開
当社は今後、さまざまな水域の水質浄化を図るとともに動植物とのふれあい(憩い)の場を提供し、豊かな水辺環境を創出する植生浄化施設「東亜リビング・フィルター」を、水辺を管理される国や地方自治体をはじめとした皆様に積極的に提案していきます。
- ※リビング・フィルターとは
- 自然界において生物体が果たしている機能や特性に注目し、これらを有効に利用することにより環境の改善・再生を促し、ひいては環境の創造をも図ろうとする環境対策の工法です。自然界において生物は何らかの形で浄化作用をもっており、多くの生物はリビング・フィルターの対象となります。
なかでもヨシやヒメガマなど大型水生植物は高い水質浄化機能を有していることが知られており、「東亜リビング・フィルター」は、こうした浄化作用や修景機能を活かした植生浄化施設になっています。